徳島大学 右手研究室のDOSY測定解説用ページ
Ute Lab DOSY Special Site
PFGパラメーター設定(DOSY仮測定)
測定の前に
Auto Gainを使用しない
90°パルス測定同様アレイ測定を行うのでAuto Gainは使用しません。
前項の90°パルス測定で得られたReceiver Gainの値で仮測定を行います。
Experimental Fileの選択
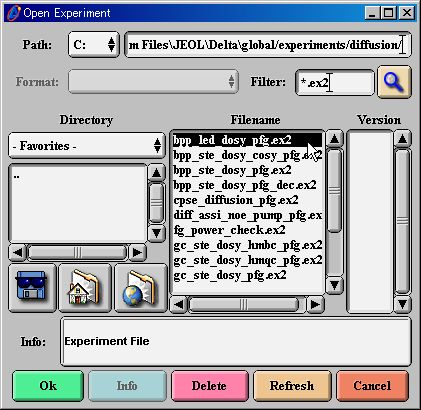
グローバル(地球儀のフォルダ)→
diffusion→bpp_led_dosy_pfg.ex2
Single Pulse測定で使用した名前とは違う名前で
保存することをオススメします。
Pulse値などの変更
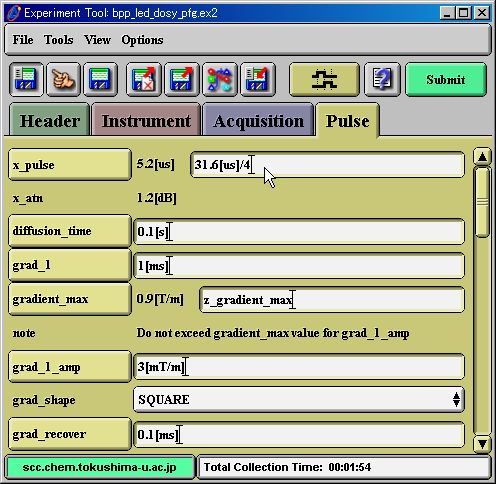
アレイタイプとその他の設定
x_pulseをクリックし前項で求めた90パルス幅を入力します。
diffusion_timeとgrad_1の値を入力します。
Duty cycleには注意してください。
grad_shapeをSQUAREに変更します。
アレイの設定
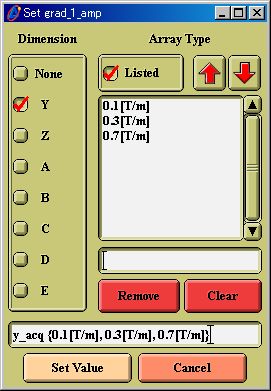
ディメンションとアレイタイプの設定
grad_1_ampのArrayを組みます。
DimentionはYチェックが入っているか確認してください。
今回はArray TypeのListedを選択します。
今回の場合は0.1[T/m],0.3[T/m],0.7[T/m]と設定します。
積算回数は多くは入りません。(2〜4回程度)
アレイデータの編集
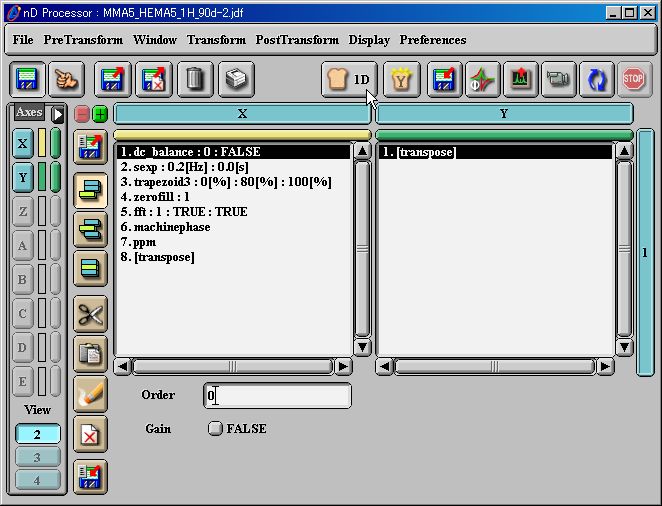
1Dボタンをクリックし、位相をある程度そろえる。
左のような画面が表示されます。
1Dボタンをクリックし磁場勾配によって歪んだ
位相をそろえます。
位相をそろえたら1Dボタンの隣にあるYボタンを
クリックしてください。
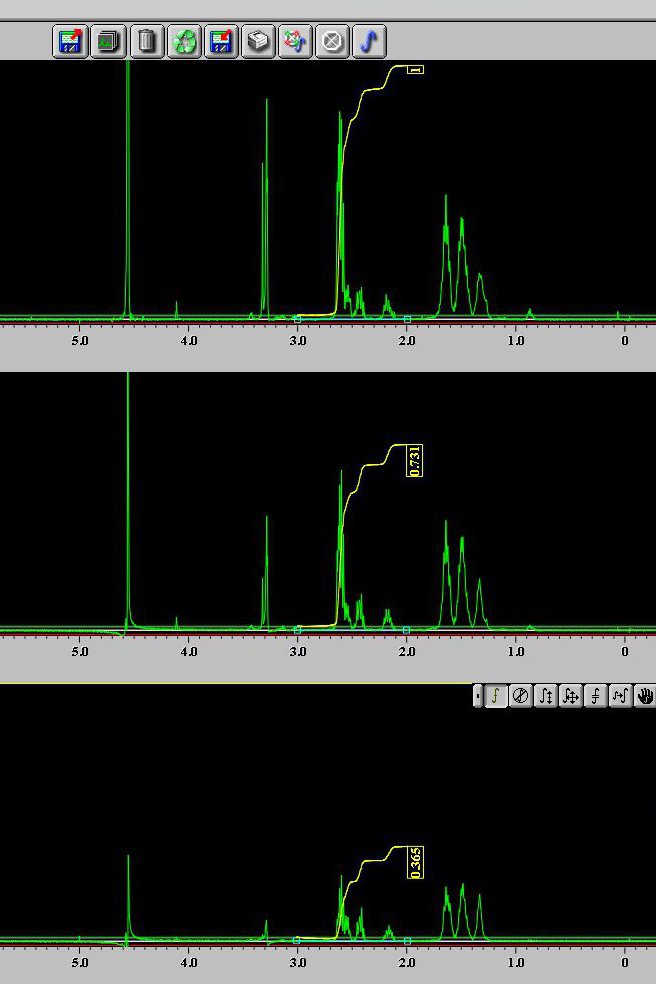
スペクトルの減衰の確認およびReceiver Gainの決定
磁場勾配が1番小さい(1番上の)スペクトルを積分します。
この時積分値を「1」とします。
残りのスペクトルも同じ範囲で積分します。
1番下のスペクトル(0.7[T/m])の積分値が、1番上ののスペクトル
(0.1[T/m])の積分値と比べ10~15%になっているか確認します。
積分値が大きいor小さい場合、diffusion_timeとgrad_1の値を変更します。
積分値が10~15%の場合、この時の測定条件で本測定をします。
測定条件が決定したら、Arrayをはずしgrad_1_ampを最小の値
(0.1[T/m])にセットし、auto_gainにチェックを入れ測定します。
積算回数は2~4改程度でかまいません。
測定終了時のReceiver Gainの値から4引いた値を本測定で
使用します。